2025年3月11日に開催された全国コミュニティ財団協会の年次大会に参加してきました。全国コミュニティ財団協会は、その名前の通り、市民性、地域性を重視する財団の連絡会です。元々はアメリカで広がり、日本では2010年頃から京都を皮切りに沖縄、岡山、佐賀などさまざまな地域で立ち上がりました。日本におけるコミュニティ財団の草創期から15年、協会設立からは10年、その間、クラウドファンディングの広がり、災害の頻発、コロナ禍、スタートアップ・ソーシャルビジネスの盛り上がりなど、社会環境はめまぐるしく変化している中で、コミュニティ財団の立ち位置を問い直すという今回の大会が開かれました。今回は、災害支援における財団の果たした役割、各機関との連携、そして市民コミュニティ財団的なプログラムオフィサーのあり方が議論されました。市民コミュニティ財団の基本的な理念は変わらずとも、社会は常に変化するものですから、財団と社会の織りなす化学反応もまた変わっていきます。ここ数年、協会は全国各地の財団立ち上げ事業を支援してきましたが、これから立ち上げようとする方々は、先例を学びながらも、今、自分たちはどのような財団でありたいのかを問いかけていました。
私は分科会「市民コミュニティ財団が備えるべきガバナンス・コンプライアンス体制の整備」でモデレーターを務めました。市民コミュニティ財団の組織としての特徴は、少人数運営が多いということ、そして寄付者も助成先も多く、したがって関係者が多いということです。これは財団の内部統制を容易成らない複雑なものにしがちです。この分科会では、弁護士による非営利組織のガバナンス支援を行う一般社団法人BLP-network代表の鬼澤秀昌氏、子どもを支援する団体を支援する合同会社コドソシ・田口由紀絵氏のお話しを伺いました。鬼澤さんからは、リスクマネジメントを、リスクの捉え方とマネジメントの仕方に分けて説明していただき、田口さんからは、パブリックリソース財団在職時のトラブル時の寄付者や助成先への対応をお話しいただきました。組織の目的・ミッションは、裏返しに、優先的に対処しなければならないリスクを示している、という(意訳ですが)鬼澤さんの言葉は、非常に考えさせるものがありました。コミュニティ財団もNPO法人、非営利組織も、概して少人数で多くの関係性の中で活動していますので、労働集約的でなく方法的なアプローチでリスクに対処したいものです。
北海道NPOファンド理事(全国コミュニティ財団協会理事) 高山
全国コミュニティ財団協会 書籍発売中「コミュニティ財団のつくりかた」
近日刊行「POの教科書」
いぞう寄付の窓口へのお問合せ
寄付募集中の基金
北のNPO基金の概要~寄付で市民活動を応援したり、基金をつくって助成を行うことができます。
北海道NPOファンドのNPO助成は、みなさまからの寄付を原資にしています。また20万円以上のご寄付で、ご自身のお考えを活かした基金を設立して助成事業を行うことができます。お気軽にお問合せください。
ご協力をお願いします
「ハンドくんファンド」は「北のNPO基金」の運営に活用させていただく基金です。運営管理経費、広報、報告会開催などに活用いたします。Yahoo!ネット募金からもご寄付が可能です(PAYPAY、Vポイントが使えます)。
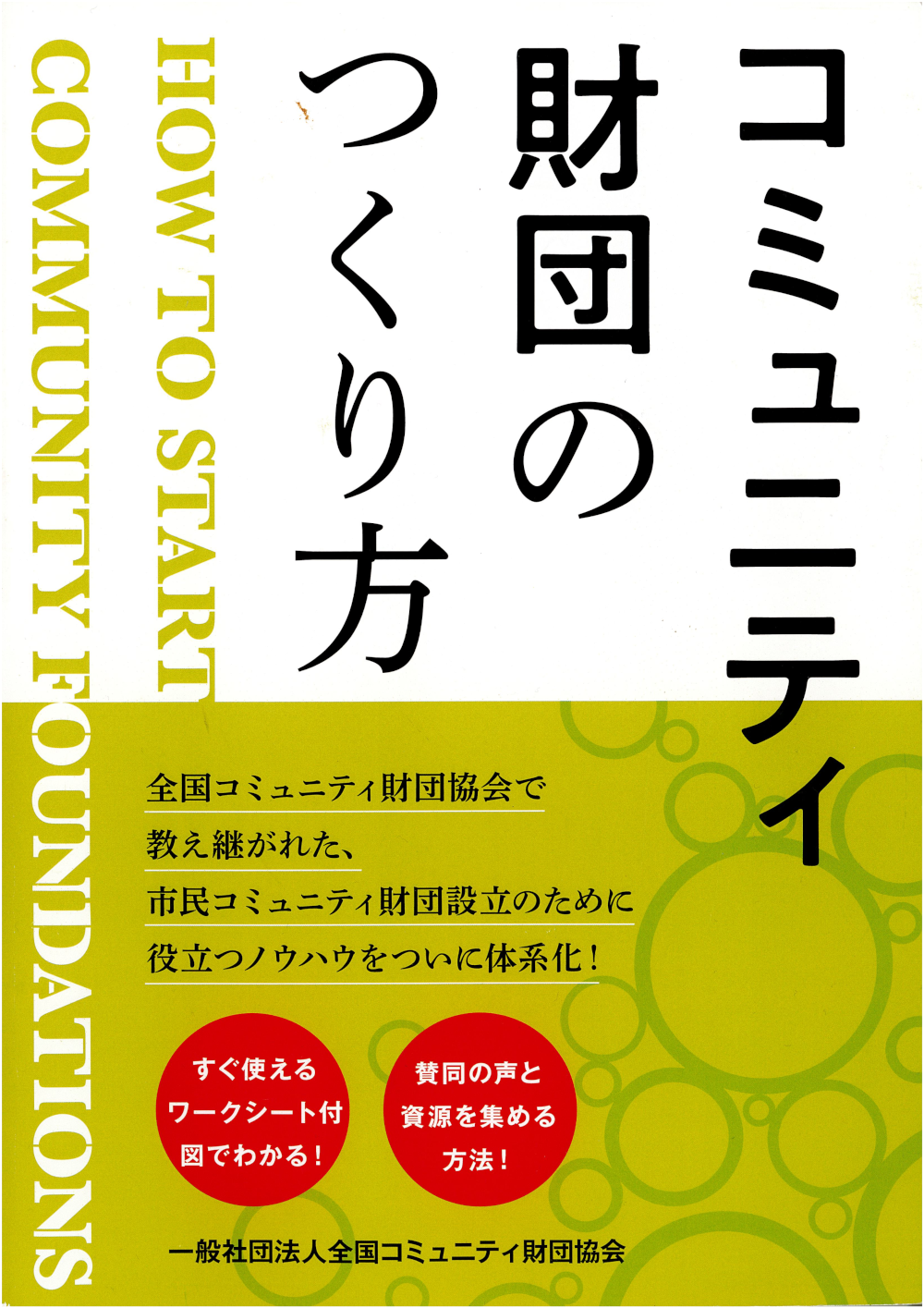
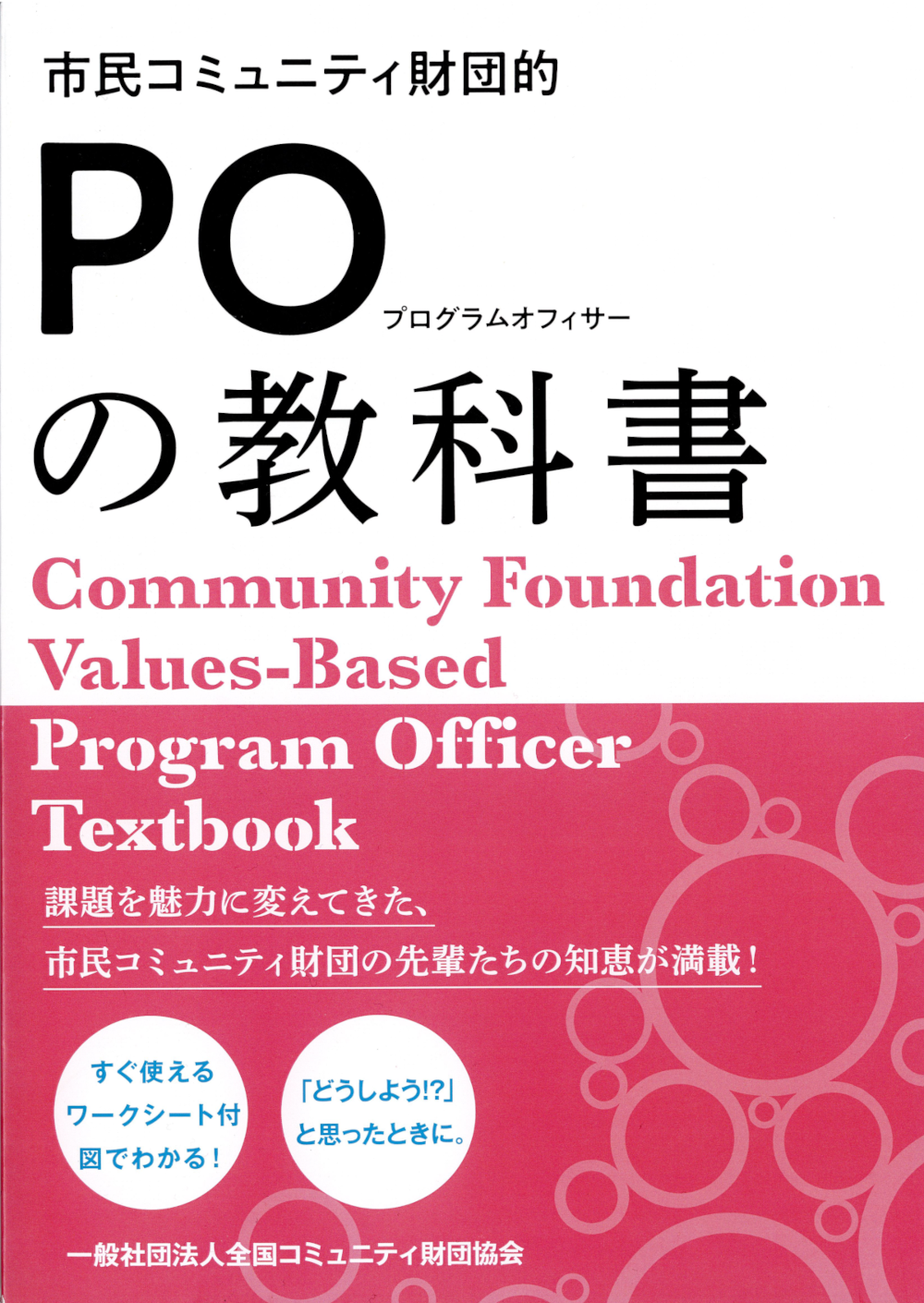


Comments are closed